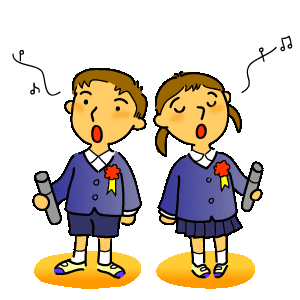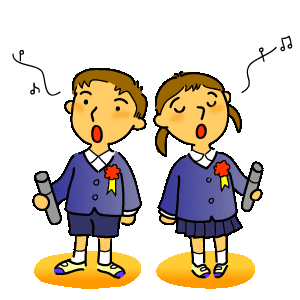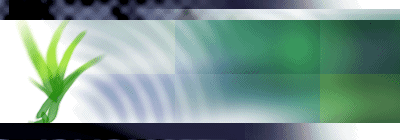●実行振動半径(a)
一般に呼ばれている口径と異なり、そのスピーカーユニットが実際音を出すために動いている主な部分
(コーン紙)等の半径を示しています。エッジの部分も一部含まれて表記される場合もあります。
●最低共振周波数(fo)
通常エフゼロと呼ばれ、その単位はHz(ヘルツ)で表示されています。低音再生の限界を決める要素とし
て見る事の出来る数値ですが、少し詳しく見て見ましょう。音叉を軽く叩くと一定の周波数の音が発生
します。これは音叉の持つ共振周波数で振動して音を出して居る為です。音叉だけで無く、すべての物
に共振周波数があります。foは最低共振周波数と呼ばれるように、その物が、最も低く共振する周波数
と言う事になります。スピーカーのfoは、振動板その物の共振とは異なり、振動する部分の等価質量
(Mo)や、それを支えるエッジやダンパー等の要素が含まれた振動系が、前後に自由振動している
周波数と見なす事が出来ます。注意点は、foはスピーカーを実際にエンクロージャー等に取り付けた
数値では無く、裸の状態での数値で有る事です。スピーカーをエンクロージャーに取り付けると、内部の
空気は、空気バネの役割を持ち、foよりも上昇する事になります。エンクロージャー設計の際、このfoの
上昇をどの辺りに設定するかが、ポイントになります。
●出力音圧レベル(S.P.L)
スピーカーの能率を示しております。1Wの入力を加えてどれくらいの音圧が(音の大きさ)得られるかを
示しています。数値が大きいほど、同じ入力を加えた時に効率良く音に変えていると考える事ができます。
たとえば、90dBと93dBのスピーカーユニットを比較した場合、90dBのスピーカーに10Wの入力を加えた時
93dBのスピーカーでは、5Wの入力で同じ音量を得る事が出来ます。フルレンジ一本で使う場合には、
特に問題は有りませんが、フルレンジ+ツィーターやウーハーとの2Way、3Wayを考えますと、つぃーたー
はウーハーより数字の大きい(高能率)な物を選びましょう。単位はdB(デシベル)で表されます。
●入力
入力は、①"最大許容入力"と ②"定格入力" 等に分けて表示されたり、どちらか一方のみ表示する
場合があります。それぞれに入力の定義が異なりますので、目的に応じてその値を確認しましょう。
①最大許容入力
この入力は、瞬間に与えられる事の出来る最大の入力を示しています。ただし、特定の周波数で測
られた値で、決してその入力まではすべての周波数で入力が可能と言う事ではありません。カタログ
に表記されている"Mus"は、一般的な音楽ソースを加えた時ピーク時に可能な入力を示していると考え
て下さい。入力の数値は、「その数値でなければ音が出ない」また、「スピーカー許容入力以下のアンプ
で無ければスピーカーが壊れる」と言う数値を示している事ではありません。 一般的に家庭内等で
聴かれてる音量では、たとえ数百W出るアンプであっても、特別な場合を除いて過大な入力が加わる
事は、極めてまれかもしれません。PAや特別実験等でスピーカーを使用する場合を除いて、家庭内で
HiFiサウンドを楽しむ場合、入力の数値は「一定の目安」として考える事も出来るでしょう。
②定格入力
この値は連続して与えられる入力の限界を示しております。ただし最大許容入力と同様に特定の周波数
で測定される値で、全ての周波数において可能な入力ではありません。測定や実験等で一定の周波数
のみを連続して入力する場合示されている入力までが、必ずしも可能とは言えません。単一の周波数を
連続して入力する事は、スピーカーにとって非常に負担の大きい動作になるでしょう。
カタログの規格の意味は??
● Qo
キュウゼロと呼ばれるこの値は、スピーカーのエンクロージャーを設計する時の重要な要素の一つです。
この値はfoにおける共振の鋭さ(共振鋭度)を示している数値です。通常、Qoは1くらいまでが良い
スピーカーとされています。
●インピーダンス(Ω)
スピーカーの入力端子インピーダンスを代表する値です。インピーダンスは一部を除いて(例えば、RP
方式ツィーター等)入力周波数によって変化します。スピーカーのインピーダンスはfo以上の周波数で
一番低下した所の値を公称インピーダンスと表します。単位はΩです。
カタログを見ると "規格" として、色々な単位で数字が表されています。
それぞれがどんな意味があるか見てみる事にしましょう。
●等価質量(Mo)
振動系の質量とその振動板にかかる前後の空気の抵抗(付加質量)を加えたものです。つまりスピー
カーが実際 前後に動いて音を出す時に発生する実質的な質量です。空気の質量も加味されている
わけですが、質量の大半は振動系の質量です。単位はg(グラム)で表示され、エムゼロと呼びます。
●推奨クロスオーバー
マルチウェイ用のスピーカーユニットに記載されている推奨クロスオーバー周波数は、中高音域用の
ユニットと低域用のユニットでは、注意点が異なります。特に注意すべき点は、ツィーターやドライバーの
場合です。中高域用のユニットでは、再生能力を超えた低域の信号が入力された場合、ユニットは破壊
(ボイスコイルの焼失等)されます。この破壊を避ける為にも、推奨クロスオーバー周波数は非常に
重要な値になります。推奨クロスオーバー周波数は、中高音用で有れば、「この周波数以上でお使い
下さい」また、低音用で有れば「この周波数以下でお使い下さい」と言う意味が含まれて居ます。
ウーハー等の低音用の場合は、推奨クロスオーバー周波数を超えた信号が入力されても、中高音の
様なユニットの破壊は起きません。低音用、中高音用いずれもの場合も、再生される音の事を考えて、
推奨値以下、以上で使用する事が望ましいでしょう。
Subページ16